「一人ひとりが幸せに生きるとは?②~前編~」
2022/07/06
司会: 山口 幹生(Blue Bullets 15期 / GM / 株式会社ポケットマルシェ取締役)
(文章:宇佐見 彰太 / 東京大学運動会ラクロス部男子Relations Manager)
山口: 今日はお時間をいただきありがとうございます。東大ラクロス部でGMを務めております山口幹生と申します。よろしくお願いいたします!
テーマは前回に引き続き「幸せとは何か?」というテーマで、東大ラクロス部を応援してくださっているGPSSグループ代表の目﨑さんと東大ラクロス部23期、READYFOR株式会社 代表取締役COOの樋浦さんという、社会課題解決を志向した事業をドライブしているお二方にお話をいただきます。
目﨑: よろしくお願いいたします。
山口: まずはオープニングコメントとして、樋浦さんから自己紹介も兼ねて、READYFORで働くに至るまでの人生の選択や、いろいろな方と関わりながら仕事をされる中で思うこと等をお話しいただけたらと思います。
1. 二人の今に至るまで
樋浦: 目﨑さん、はじめまして。よろしくお願いします。
自分の原体験のような部分で言うと、ラクロス部での活動が自分の人格形成の根幹だったと思っています。今はREADYFORという会社の経営に携わっていますが、実際にラクロス部での原体験が組織づくりに活きています。
山口:実際にどのような点が組織作りに活きていますか?
樋浦: ラクロスって、ひとりひとりの個性を活かせるスポーツだと思っていて、僕自身はATという点を取るポジションでしたが、DFが上手い人もいれば、パスが上手い人もいる。異なった個性をもつメンバーの間でシナジーが生まれて、良いプレーが生まれたときの達成感や楽しさをラクロスから学びました。READYFORでも、ひとりひとりが違う前提で、それぞれが強みやエネルギーを発揮して活躍できる場をつくることに取り組んでいます。

2010シーズンを駆け抜けたラクロス部23期
山口: 以前はボストン・コンサルティング・グループ(BCG)で活躍されてましたね。
樋浦: はい。大学を出てBCGという会社に就職して働く中で、自分自身はビジョンやカリスマ性で人を引っ張るのは得意ではないけれど、誰かの描いている絵を言語化したり、道筋をつけることは得意だと気付きました。現役時代は副将で、主将の山下(23期主将 山下尚志)がまさに直感が優れていてビジョナリーなタイプ。山下が見ている方向に進めば、素晴らしいチームになるし、結果に繋がると肌で感じていましたが、本人はなんでそっちに行きたいのか、どう行けばいいのかわからない。それを言語化しながら手伝っていくことは自分にとってやりがいがあるし、自分の価値を最大化できる。それこそ、幸せに生きていくことに繋がるのではないかと感じたことが原体験となって、想い溢れる人を支えるためにコンサルタントを志しました。
山口: そこからREADYFORに転職したのはなぜですか?
樋浦: それから4年経って、READYFORの創業者でCEOである米良さんに出会いました。ちょうどREADYFORは経営チームを探していたところで、 そのことを友人から紹介してもらい、 すぐに会って、土日ぶっ続けで話をして、その場で転職を決めました。早く意思決定できた理由は、3つの条件が重なっていたからです。
山口: その「3つの条件」は何だったのでしょうか。
樋浦: 1つ目は、READYFORが個々人の意志を尊重し、それを応援する事業をやっていて、自分の価値観に合っていたからです。2つ目は、米良さんがビジョナリーで、自分が応援したい経営者像そのものだったから。そして、3つ目は、この若さで経営に関われる機会はそうそうないと思ったからです。そこから7年間、ずっと一緒にやってきています。

Readyfor株式会社にて
山口: なるほどなるほど。「幸せに生きる」うえで、「やりたいこと」と「得意なこと」のどちらを選ぶべきかについて、後ほど聞かせてください。続いて目﨑さんからこれまでの歩みについて伺えたらと思います。
目﨑: 僕はアメリカの証券会社に勤めてから、10年間世界を放浪していました。就職のときには、多くの人が会社に就職するという日本社会のあり方に疑問を持っていて、起業して経営していくことが自分のやりたいことに繋がるのではないかと思っていました。そうは言っても起業したいサービスが決まっているわけではなかったので、起業のノウハウを最短で最大限学べるのは外資系だと思い、アメリカの証券会社に入ったのです。
山口: いつか起業しようという想いで就職されたんですね。
目﨑: はい。証券会社に入って、トレーディングを担当していました。まさに資本主義の再現といった仕事で、得意でもあり面白かったのですが、ただ利益を追求するだけのトレーディングが得意な自分が嫌になっていきました。このままでは自分がなりたい人物像になれないと思い、5年で退職しました。このとき、起業して会社を大きくしていくことも「最小限の投資から最大限の利益を追求すること」であって、本質的には同じことだと思い、起業についても興味がなくなってしまいました。
山口: 退職して、起業にも興味がなくなって、その先はどうされたんですか?
目﨑: 退職後、魂を浄化させるしかないと思い、インドに行きました。放浪しながら、幸せについて考えていました。その中で、個人が体感できる刹那的な快楽には限界がある、もっと大きな喜びは、他人の役に立っているか、自分自身の本質的な存在意義を感じられるか、自分の命が他人に対してどれだけ意味があるかということなのだと感じました。そこで何ができるかを考えたときに、自分の得意なことをやりたい、と思ったのです。他の人よりも結果が出せるものを使って、世の中にはたらきかける方がより大きな喜びにつながる。そう思いました。
山口: 具体的にはどのような形で行動に移されたのですか?
目﨑: それならば、日本に戻ることが最善だと思いました。日本社会のあり方に多くの疑問を感じていましたが、逆に言えば日本人がそれらの問題を問題だと思っていないことが最大の問題なのではないかと。幸せのために生きている人がほとんどいなくて、そのことを認識している人もほとんどいない。それを解決することこそ、人生をかける価値があるのではないかと思い、日本に戻りました。
山口: それからGPSSグループを創業されたのですね。
目﨑: 会社は多くの人が多くの時間と多大なエネルギーを費やすコミュニティだから、よい働き方ができる場であるとともに、事業自体が社会的な意義のあるものでなければならないと思いました。GPSSグループは再生可能エネルギーによる発電所の建設と、それら発電所による発電事業を主たる事業としていますが、自然エネルギーの発電所を造れば造るほど、自社の利益にもなるし、発電所から生み出される持続可能なエネルギーは社会のためになっていて、利益と社会貢献が直結している。地球規模でマーケットがあり、同時に地球規模で直面している課題に挑戦できるのが壮大でチャレンジングでした。そこでの組織のつくり方について、自分なりの「人間はどう生きるべきか」という思考をしながら事業を始めて、いまは道半ばです。
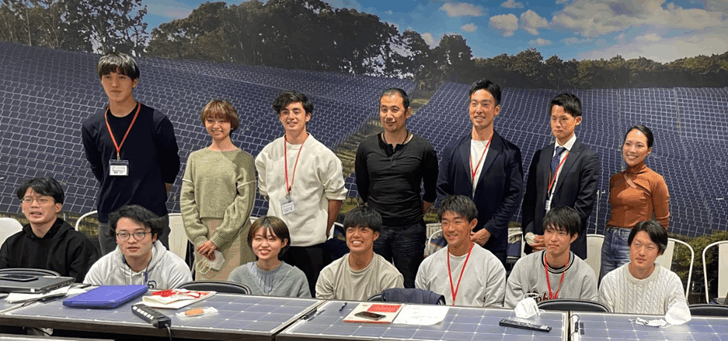
GPSSグループ 東大ラクロス部インターンシップ
2. 幸せに向き合うようになった転換点
樋浦: 「地球は燃やさない。魂、燃やせ。」という理念はエネルギーをもらえる言葉ですね。目﨑さんが「日本社会において人は幸せになれるのか」と感じた背景や、そう考えるようになったきっかけについてお聞きしたいです。
目﨑: 大学時代にフランスに短期留学に行きました。周りの同じ歳くらいの大学生と仲良くなっていく中で、現地の大学生たちが主体的に生きていて、とても魅力的に映りました。それまでは自分も日本社会ももっと「イケてるだろう」と思っていたのですが、すごく劣等感を感じたのです。当時はまだ言語化できていませんでしたが、それが語学的な問題ではないことは自分なりにわかっていました。直感的に、彼らの方が自分よりずっと幸せじゃないかという認識がありました。
山口: 現地の大学生との差を感じて、どうされたんですか?
目﨑: 自分も彼らと同じように育っていたら、もっと面白い人間になっていたと思うとすごく頭にきました。それならばと、これまで強制の中で学んできたことをリセットして、自分の中にある日本人らしさを取り除けばよいと思ったのです。それが、日本社会をいかに客観的に分析するか、社会とは何なのか、人間とは何なのか、幸せとは何なのかということについて主体的に考え始めたきっかけでした。
樋浦: 僕の場合は、29歳でパラダイムシフトが起きました。きっかけは、働きすぎで燃え尽きかけてしまったことがあって、「このままだとヤバいな」というときに時に、コーチングと出会ったことでした。
山口: どのようなコーチングを受けたのですか?
樋浦: コーチ に「人生が100点満点だとしたら、今、君の人生は何点なの?」と聞かれて、「85点」と答えました。死にかけだと思っていたのですが、意外と高い点数で、自分は幸せだと思っていることに気づくとともに、「残りの15点は何なの?」と聞かれて、「もっとエネルギー高くワクワクしながら生きたい」という答えが自然に出てきて、「ああ、自分はワクワクしながらエネルギー高く生きたいんだ」と初めて気づきました。
山口: コーチングを受けて、自分の志向を言語化できたのですね。
樋浦: そこから自分はどうしたらワクワクするのか、エネルギー高くいられるのかという問いが始まり、自分自身への理解が深まって、その結果として人はそれぞれエネルギーが高まる方法が違うということにも気づいて、すごく世界が広がりました。ここにきて、日本で29年生きてきて、誰もそのことを問いかけてくれなかったことに気づきました。「あなたはどうあれば幸せになれるのか」「どうあれば元気にいられるのか」を一度も訊いてくれなかったなと。「どこに進学するんですか」「どこに就職するんですか」は訊かれても、人それぞれに違うはずの「あなたの幸せ」について問いかけてはくれない。問いかけてくれないから、考えるという発想がないし、「人はそれぞれに違う」ということを社会に落とし込めていないことが日本の大きな問題ではないかと思っています。学校の先生もそれを問われてこなかったから生徒に対して問えないのだと思うと、構造的な課題なのだろうなと思いました。

太陽光パネルをかたどったデスクにて会議の様子
3. 好きなことを見つける
目﨑: 日本では、子どもに対して一番に教えるのは「ダメなこと」ですよね。身体的な安全を確保することは重要ですが、「こうあるべき」「常識」と言われるものがあって、平均値から欠け目がないことが正しいのだと徹底的に植えつけられる。「自分は何がしたいのか、何が好きなのか」ということは関係ない。それが全部できたら、好きなことをやりなさいという教育がされている。
山口: 確かに、そういう傾向が強いですね。
目﨑: そういった環境で育つうちに、自分の内面にある「これが好き」「これがしたい」という感情はどんどん抑圧されてしまって、育たなくなってしまいます。人の期待に応えることにすごく長けていて、頭が良くて順応能力が高い人が「優等生」。不幸ではないと思いますが、幸せでもないですよね。 樋浦: 不幸じゃない、というのも重要だと思っています。放り出されて、好きにしろというのも人によってはつらい。高度経済成長期と呼ばれていた時期は 、学歴を積んで、役割を果たせる人が偉くなって、結婚して、子どもを産んでという「幸せ」がパッケージ化されていた時代だったのかなと想像しています 。
山口: 「夢のマイホーム」とか、皆が目指す「幸せ」の像が明確だった時代ですね。
樋浦: それって、できるだけ多くの人が幸せになる確率を高めるためにつくられてきた一種の制度なのだろうなと思うけれど、「今の時代にみんなが幸せになる方法」にアップデートされていないのではないかと思います。
目﨑: 就職のタイミングはカギになると思います。それまでは、「これをやらなければならない」という共通概念が明確にありますが、いざ成人して「好きなことをやりなさい」と言われたときに、生まれてから好きなことをやってこなかったから「好きなこと」が何なのかがわからない。
樋浦: 常識にアジャストする一方、人との違いを深堀ってきた経験が少ないために「だいたい他の人も自分と同じ考えだろう」と思っている人が多いように思います。そうすると自分の強みや「好きなこと」がわからないから、それを職業や技能という型にはめて考える人が多いですよね。
目﨑: 人生と職業が一致していると思ってしまうのはナンセンスです。時代によってどんどん変わる「職業」と、人生という長いものを一緒にする発想自体を変えなければならないと思います。人類の歴史を俯瞰的に見ると、西洋も東洋も関係なく、人類の考え方がより「どう生きるか」という主体的な方向へと流れていく中で、若干の地域的・時間的なズレがあるだけなのだということかとも思います。
樋浦: そうですね、日本はひとつ前の時代に適応した概念をつくり切ってしまったところがあると思います。目﨑さんのおっしゃる通りで、俯瞰的に見れば人類が過ごしてきたほとんどの時間において、そもそも「人権」という概念もなかったわけで、最近になって安心して生きていける人が増えてきてい て、「どう生きるのか?」が問われ始めているのだと思うと、いい時代になってきているとも言えると思います。
目﨑: 人類は生命の安全がある程度保証されたからこそ「生きている意味」を問い始めてしまい、答えを出さなければいけないと考えるようになったということですね。「生きる意味」については、過去には宗教など外部から無条件で与えられてきたけれど、科学的知識や教養を持つようになって、自分自身の意識において主体的に自身の人生観や存在意義をつくり上げていかないと満足できない時代になっています。

2020年のGPSS研修旅行

樋浦さんと安西渉さん
樋浦: そういった時代にあって、目﨑さんご自身の「幸せ」とはなんですか?
目﨑: 優等生的な答えとしては、やはり自分自身の社会における役割と、それを通じた貢献というのは非常に大きいです。でも「本当に何に自分の魂が燃えているのですか?」という質問であると捉えると、アルゼンチンタンゴをどこまで突き詰めてやるかという話になってきますね。
樋浦: アルゼンチンタンゴの話、前回の対談で語っていただいていましたね。気になる方は前回の対談も読んでみてください!(笑)
目﨑: 自分がやりたいことがどこから来ているのかと考えたときに、生まれ持った特性や社会的な環境も自分で決めたものではないので、それは本当の意味で自由に決めたことではないのではないかと思って。ヒッピーをやっていた時代には、それらの制約を排除した人生を歩むために、行きたいところに行って、やりたいことを全部やってみました。
樋浦: なるほど。
目﨑: 社会環境によって好きだと思わされていることを排除して、自分の内側から湧き上がってくる「好き」を見出したい。「日本人として生まれたから味噌汁が好きだ」ではなくて、「実際に味噌汁を飲んで結果的にそれが好きだから好きだ」というような感じです。そのためには、自分の中から日本社会的な要因を排除する必要がありました。
樋浦: その結果、どうなったんですか?
目﨑: 突き詰めていくと、自分の内側から「これしかない」という感覚のものが出てきます。アルゼンチンタンゴがそれなのですが、No Choiceという感覚です。そうすると今度は自分で選んでいる感覚が一切ない。その結果、私たちは自由が素晴らしいと思っているけど、本質的には自由を求めているわけではないのかなと思いました。
樋浦: 制約のない自由に価値を置いているからこそ、突き詰めると自由すら自由でなくなってしまって、そこに生きづらさを感じるということですね。
目﨑: そうです。「自由」は概念としては重要ですが、究極的には、我々を幸せにする一つの材料としては不十分だと思います。
続きは後編をご覧ください。
(文章:宇佐見 彰太 / 東京大学運動会ラクロス部男子Relations Manager)
山口: 今日はお時間をいただきありがとうございます。東大ラクロス部でGMを務めております山口幹生と申します。よろしくお願いいたします!
テーマは前回に引き続き「幸せとは何か?」というテーマで、東大ラクロス部を応援してくださっているGPSSグループ代表の目﨑さんと東大ラクロス部23期、READYFOR株式会社 代表取締役COOの樋浦さんという、社会課題解決を志向した事業をドライブしているお二方にお話をいただきます。
目﨑: よろしくお願いいたします。
山口: まずはオープニングコメントとして、樋浦さんから自己紹介も兼ねて、READYFORで働くに至るまでの人生の選択や、いろいろな方と関わりながら仕事をされる中で思うこと等をお話しいただけたらと思います。
1. 二人の今に至るまで
樋浦: 目﨑さん、はじめまして。よろしくお願いします。
自分の原体験のような部分で言うと、ラクロス部での活動が自分の人格形成の根幹だったと思っています。今はREADYFORという会社の経営に携わっていますが、実際にラクロス部での原体験が組織づくりに活きています。
山口:実際にどのような点が組織作りに活きていますか?
樋浦: ラクロスって、ひとりひとりの個性を活かせるスポーツだと思っていて、僕自身はATという点を取るポジションでしたが、DFが上手い人もいれば、パスが上手い人もいる。異なった個性をもつメンバーの間でシナジーが生まれて、良いプレーが生まれたときの達成感や楽しさをラクロスから学びました。READYFORでも、ひとりひとりが違う前提で、それぞれが強みやエネルギーを発揮して活躍できる場をつくることに取り組んでいます。

2010シーズンを駆け抜けたラクロス部23期
山口: 以前はボストン・コンサルティング・グループ(BCG)で活躍されてましたね。
樋浦: はい。大学を出てBCGという会社に就職して働く中で、自分自身はビジョンやカリスマ性で人を引っ張るのは得意ではないけれど、誰かの描いている絵を言語化したり、道筋をつけることは得意だと気付きました。現役時代は副将で、主将の山下(23期主将 山下尚志)がまさに直感が優れていてビジョナリーなタイプ。山下が見ている方向に進めば、素晴らしいチームになるし、結果に繋がると肌で感じていましたが、本人はなんでそっちに行きたいのか、どう行けばいいのかわからない。それを言語化しながら手伝っていくことは自分にとってやりがいがあるし、自分の価値を最大化できる。それこそ、幸せに生きていくことに繋がるのではないかと感じたことが原体験となって、想い溢れる人を支えるためにコンサルタントを志しました。
山口: そこからREADYFORに転職したのはなぜですか?
樋浦: それから4年経って、READYFORの創業者でCEOである米良さんに出会いました。ちょうどREADYFORは経営チームを探していたところで、 そのことを友人から紹介してもらい、 すぐに会って、土日ぶっ続けで話をして、その場で転職を決めました。早く意思決定できた理由は、3つの条件が重なっていたからです。
山口: その「3つの条件」は何だったのでしょうか。
樋浦: 1つ目は、READYFORが個々人の意志を尊重し、それを応援する事業をやっていて、自分の価値観に合っていたからです。2つ目は、米良さんがビジョナリーで、自分が応援したい経営者像そのものだったから。そして、3つ目は、この若さで経営に関われる機会はそうそうないと思ったからです。そこから7年間、ずっと一緒にやってきています。

Readyfor株式会社にて
山口: なるほどなるほど。「幸せに生きる」うえで、「やりたいこと」と「得意なこと」のどちらを選ぶべきかについて、後ほど聞かせてください。続いて目﨑さんからこれまでの歩みについて伺えたらと思います。
目﨑: 僕はアメリカの証券会社に勤めてから、10年間世界を放浪していました。就職のときには、多くの人が会社に就職するという日本社会のあり方に疑問を持っていて、起業して経営していくことが自分のやりたいことに繋がるのではないかと思っていました。そうは言っても起業したいサービスが決まっているわけではなかったので、起業のノウハウを最短で最大限学べるのは外資系だと思い、アメリカの証券会社に入ったのです。
山口: いつか起業しようという想いで就職されたんですね。
目﨑: はい。証券会社に入って、トレーディングを担当していました。まさに資本主義の再現といった仕事で、得意でもあり面白かったのですが、ただ利益を追求するだけのトレーディングが得意な自分が嫌になっていきました。このままでは自分がなりたい人物像になれないと思い、5年で退職しました。このとき、起業して会社を大きくしていくことも「最小限の投資から最大限の利益を追求すること」であって、本質的には同じことだと思い、起業についても興味がなくなってしまいました。
山口: 退職して、起業にも興味がなくなって、その先はどうされたんですか?
目﨑: 退職後、魂を浄化させるしかないと思い、インドに行きました。放浪しながら、幸せについて考えていました。その中で、個人が体感できる刹那的な快楽には限界がある、もっと大きな喜びは、他人の役に立っているか、自分自身の本質的な存在意義を感じられるか、自分の命が他人に対してどれだけ意味があるかということなのだと感じました。そこで何ができるかを考えたときに、自分の得意なことをやりたい、と思ったのです。他の人よりも結果が出せるものを使って、世の中にはたらきかける方がより大きな喜びにつながる。そう思いました。
山口: 具体的にはどのような形で行動に移されたのですか?
目﨑: それならば、日本に戻ることが最善だと思いました。日本社会のあり方に多くの疑問を感じていましたが、逆に言えば日本人がそれらの問題を問題だと思っていないことが最大の問題なのではないかと。幸せのために生きている人がほとんどいなくて、そのことを認識している人もほとんどいない。それを解決することこそ、人生をかける価値があるのではないかと思い、日本に戻りました。
山口: それからGPSSグループを創業されたのですね。
目﨑: 会社は多くの人が多くの時間と多大なエネルギーを費やすコミュニティだから、よい働き方ができる場であるとともに、事業自体が社会的な意義のあるものでなければならないと思いました。GPSSグループは再生可能エネルギーによる発電所の建設と、それら発電所による発電事業を主たる事業としていますが、自然エネルギーの発電所を造れば造るほど、自社の利益にもなるし、発電所から生み出される持続可能なエネルギーは社会のためになっていて、利益と社会貢献が直結している。地球規模でマーケットがあり、同時に地球規模で直面している課題に挑戦できるのが壮大でチャレンジングでした。そこでの組織のつくり方について、自分なりの「人間はどう生きるべきか」という思考をしながら事業を始めて、いまは道半ばです。
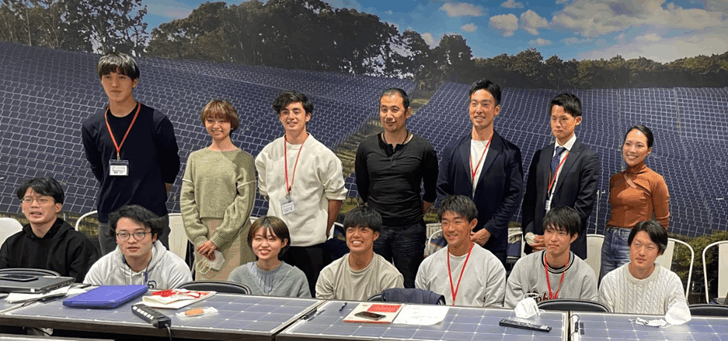
GPSSグループ 東大ラクロス部インターンシップ
2. 幸せに向き合うようになった転換点
樋浦: 「地球は燃やさない。魂、燃やせ。」という理念はエネルギーをもらえる言葉ですね。目﨑さんが「日本社会において人は幸せになれるのか」と感じた背景や、そう考えるようになったきっかけについてお聞きしたいです。
目﨑: 大学時代にフランスに短期留学に行きました。周りの同じ歳くらいの大学生と仲良くなっていく中で、現地の大学生たちが主体的に生きていて、とても魅力的に映りました。それまでは自分も日本社会ももっと「イケてるだろう」と思っていたのですが、すごく劣等感を感じたのです。当時はまだ言語化できていませんでしたが、それが語学的な問題ではないことは自分なりにわかっていました。直感的に、彼らの方が自分よりずっと幸せじゃないかという認識がありました。
山口: 現地の大学生との差を感じて、どうされたんですか?
目﨑: 自分も彼らと同じように育っていたら、もっと面白い人間になっていたと思うとすごく頭にきました。それならばと、これまで強制の中で学んできたことをリセットして、自分の中にある日本人らしさを取り除けばよいと思ったのです。それが、日本社会をいかに客観的に分析するか、社会とは何なのか、人間とは何なのか、幸せとは何なのかということについて主体的に考え始めたきっかけでした。
樋浦: 僕の場合は、29歳でパラダイムシフトが起きました。きっかけは、働きすぎで燃え尽きかけてしまったことがあって、「このままだとヤバいな」というときに時に、コーチングと出会ったことでした。
山口: どのようなコーチングを受けたのですか?
樋浦: コーチ に「人生が100点満点だとしたら、今、君の人生は何点なの?」と聞かれて、「85点」と答えました。死にかけだと思っていたのですが、意外と高い点数で、自分は幸せだと思っていることに気づくとともに、「残りの15点は何なの?」と聞かれて、「もっとエネルギー高くワクワクしながら生きたい」という答えが自然に出てきて、「ああ、自分はワクワクしながらエネルギー高く生きたいんだ」と初めて気づきました。
山口: コーチングを受けて、自分の志向を言語化できたのですね。
樋浦: そこから自分はどうしたらワクワクするのか、エネルギー高くいられるのかという問いが始まり、自分自身への理解が深まって、その結果として人はそれぞれエネルギーが高まる方法が違うということにも気づいて、すごく世界が広がりました。ここにきて、日本で29年生きてきて、誰もそのことを問いかけてくれなかったことに気づきました。「あなたはどうあれば幸せになれるのか」「どうあれば元気にいられるのか」を一度も訊いてくれなかったなと。「どこに進学するんですか」「どこに就職するんですか」は訊かれても、人それぞれに違うはずの「あなたの幸せ」について問いかけてはくれない。問いかけてくれないから、考えるという発想がないし、「人はそれぞれに違う」ということを社会に落とし込めていないことが日本の大きな問題ではないかと思っています。学校の先生もそれを問われてこなかったから生徒に対して問えないのだと思うと、構造的な課題なのだろうなと思いました。

太陽光パネルをかたどったデスクにて会議の様子
3. 好きなことを見つける
目﨑: 日本では、子どもに対して一番に教えるのは「ダメなこと」ですよね。身体的な安全を確保することは重要ですが、「こうあるべき」「常識」と言われるものがあって、平均値から欠け目がないことが正しいのだと徹底的に植えつけられる。「自分は何がしたいのか、何が好きなのか」ということは関係ない。それが全部できたら、好きなことをやりなさいという教育がされている。
山口: 確かに、そういう傾向が強いですね。
目﨑: そういった環境で育つうちに、自分の内面にある「これが好き」「これがしたい」という感情はどんどん抑圧されてしまって、育たなくなってしまいます。人の期待に応えることにすごく長けていて、頭が良くて順応能力が高い人が「優等生」。不幸ではないと思いますが、幸せでもないですよね。 樋浦: 不幸じゃない、というのも重要だと思っています。放り出されて、好きにしろというのも人によってはつらい。高度経済成長期と呼ばれていた時期は 、学歴を積んで、役割を果たせる人が偉くなって、結婚して、子どもを産んでという「幸せ」がパッケージ化されていた時代だったのかなと想像しています 。
山口: 「夢のマイホーム」とか、皆が目指す「幸せ」の像が明確だった時代ですね。
樋浦: それって、できるだけ多くの人が幸せになる確率を高めるためにつくられてきた一種の制度なのだろうなと思うけれど、「今の時代にみんなが幸せになる方法」にアップデートされていないのではないかと思います。
目﨑: 就職のタイミングはカギになると思います。それまでは、「これをやらなければならない」という共通概念が明確にありますが、いざ成人して「好きなことをやりなさい」と言われたときに、生まれてから好きなことをやってこなかったから「好きなこと」が何なのかがわからない。
樋浦: 常識にアジャストする一方、人との違いを深堀ってきた経験が少ないために「だいたい他の人も自分と同じ考えだろう」と思っている人が多いように思います。そうすると自分の強みや「好きなこと」がわからないから、それを職業や技能という型にはめて考える人が多いですよね。
目﨑: 人生と職業が一致していると思ってしまうのはナンセンスです。時代によってどんどん変わる「職業」と、人生という長いものを一緒にする発想自体を変えなければならないと思います。人類の歴史を俯瞰的に見ると、西洋も東洋も関係なく、人類の考え方がより「どう生きるか」という主体的な方向へと流れていく中で、若干の地域的・時間的なズレがあるだけなのだということかとも思います。
樋浦: そうですね、日本はひとつ前の時代に適応した概念をつくり切ってしまったところがあると思います。目﨑さんのおっしゃる通りで、俯瞰的に見れば人類が過ごしてきたほとんどの時間において、そもそも「人権」という概念もなかったわけで、最近になって安心して生きていける人が増えてきてい て、「どう生きるのか?」が問われ始めているのだと思うと、いい時代になってきているとも言えると思います。
目﨑: 人類は生命の安全がある程度保証されたからこそ「生きている意味」を問い始めてしまい、答えを出さなければいけないと考えるようになったということですね。「生きる意味」については、過去には宗教など外部から無条件で与えられてきたけれど、科学的知識や教養を持つようになって、自分自身の意識において主体的に自身の人生観や存在意義をつくり上げていかないと満足できない時代になっています。

2020年のGPSS研修旅行

樋浦さんと安西渉さん
樋浦: そういった時代にあって、目﨑さんご自身の「幸せ」とはなんですか?
目﨑: 優等生的な答えとしては、やはり自分自身の社会における役割と、それを通じた貢献というのは非常に大きいです。でも「本当に何に自分の魂が燃えているのですか?」という質問であると捉えると、アルゼンチンタンゴをどこまで突き詰めてやるかという話になってきますね。
樋浦: アルゼンチンタンゴの話、前回の対談で語っていただいていましたね。気になる方は前回の対談も読んでみてください!(笑)
目﨑: 自分がやりたいことがどこから来ているのかと考えたときに、生まれ持った特性や社会的な環境も自分で決めたものではないので、それは本当の意味で自由に決めたことではないのではないかと思って。ヒッピーをやっていた時代には、それらの制約を排除した人生を歩むために、行きたいところに行って、やりたいことを全部やってみました。
樋浦: なるほど。
目﨑: 社会環境によって好きだと思わされていることを排除して、自分の内側から湧き上がってくる「好き」を見出したい。「日本人として生まれたから味噌汁が好きだ」ではなくて、「実際に味噌汁を飲んで結果的にそれが好きだから好きだ」というような感じです。そのためには、自分の中から日本社会的な要因を排除する必要がありました。
樋浦: その結果、どうなったんですか?
目﨑: 突き詰めていくと、自分の内側から「これしかない」という感覚のものが出てきます。アルゼンチンタンゴがそれなのですが、No Choiceという感覚です。そうすると今度は自分で選んでいる感覚が一切ない。その結果、私たちは自由が素晴らしいと思っているけど、本質的には自由を求めているわけではないのかなと思いました。
樋浦: 制約のない自由に価値を置いているからこそ、突き詰めると自由すら自由でなくなってしまって、そこに生きづらさを感じるということですね。
目﨑: そうです。「自由」は概念としては重要ですが、究極的には、我々を幸せにする一つの材料としては不十分だと思います。
続きは後編をご覧ください。
